| 東亜医学協会会員店 |
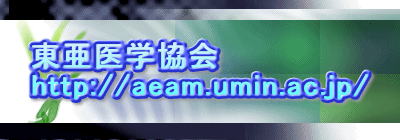 |
|
|
|
四診というのは
望診(ボウシン)、聞診(ブンシン)、問診(モンシン)、切診(セツシン)の4つの診察方です。
望診は視覚で 患者さんの体形・顔色・眼・皮膚・姿勢・身体の動かし方などを観察する方法です。
望診の中に舌診があります。舌診とは患者さんの舌の様子で内臓熱・水毒の程度・血滞・血熱・
病の虚実まで舌を診るだけで病態を知る事が出来ます。
聞診は耳で患者さんの声・咳・呼吸音・腹鳴を聞いたり(聴覚)、
体臭・口臭・大小便・分泌物(臭覚)などの臭いを嗅ぐ方法です。
問診は「患者さんの訴え」を聞く事です。漢方では「患者さんの訴え」を最も重要視します。
それは一人一人の体質も、病状も違うからです。
切診は手で直接触れて脈診や腹診をする方法です。
日本には独特の腹診法があります。
四診をから得た患者さんの訴えをもとに、陰陽●気・血・水● 表裏●寒熱という
診断基準となるいくつかのものさしで証を決定します。
西洋医学の診断は、病名を決定し、その後、治療法を決定していきます。
一方、漢方医学では証を決定するという診断と、同時に治療法も決定します。 |